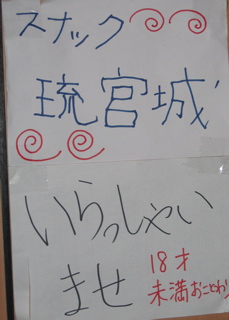3月24, 25日ロンドン

ケンブリッジで開催される学会に出席するついでに、ロンドンに立ち寄った。ロンドンでは郊外のHern Hillにあるラ・サール会修道院に宿泊した。 私が卒業したラ・サール学園中学・高等学校は、カトリック系ラ・サール修道会の学校であったため、これまで外国に寄る時はしばしば現地のラ・サール会修道院に宿泊することがあった。修道院には必ずゲストルームがあり、修道士達は、来客をもてなすことも職務の一つであるため、毎度丁寧なおもてなしを受けていた。但し、彼らと寝食を共にし、定時には共に祈りをささげないといけないため、彼らのペースに生活リズムを合わせないといけない。また、女人禁制であるため、女性同伴の旅行の際は訪問がはばかられ、おそらく独身の間しか利用しないであろう。 その日も早めに夕食を済ませ、修道士の一人が、聖職者とは思えない程豪快なハンドルさばきで、夜のロンドンを案内してくれた。21年ぶりのロンドンは、幼いころの記憶とほとんど変わった感はなかったが、21年前はとても街とテムズ川が汚かった記憶があった。しかし、この時は街が幾分綺麗になっており、修道士が言うにはテムズ川にも魚が戻ってきたそうだ。翌日はウェストミンスター寺院、ビッグベン、作曲家ヘンデルの墓とヘンデルが住んでいたヘンデルハウス、王立音楽アカデミーなどを訪れた。21年前にここで家族とチャールズ皇太子の行幸を待っていたが、あまりにも遅くなりすぎて、その一行を見られなかった時のことを思い出した。